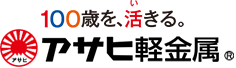お知らせ
活力なべ(圧力鍋)で初めて炊飯に挑戦!

当社では、新入社員に自社製品をしっかり理解してもらうため、料理研修なるものがあります。製品を実際に使って、レポートにまとめて上司に提出するのです。このコラムでは、そんな新入社員が実際に作成したレポートをご紹介。第1回目は、活力なべ(圧力鍋)で「白ごはん」作り! 炊飯器よりも時間がかからず、モチモチ食感のごはんができるんです。(2016年4月19日作成)
初めまして。
このたびアサヒ軽金属工業に調理器具デザイナーとして入社した「新入りN」と申します。
まだまだ新人の私ですが、ゆくゆくは鍋やフライパンのデザインを担当して、お客様に喜んでいただけるものづくりをしたいと思っています。
さて、この会社で新入社員を待ち構える最初の難関は「料理研修」です。自社製品を使って料理を作り、レポートにまとめます。作成したレポートは、直属の上司や常務、そして社長にまで回覧されます。
↓実際に私が会社に提出した料理レポート

料理を作ることが難関というわけではありません。
料理経験がなかった私でも、アサヒの調理器具とレシピ集があればちゃんと料理が作れたのですから!難関は、レポートを書くことでした。
「社長や常務に君を印象づけられる、おもしろいレポートにすること」
これはレポートを書き始める前に上司から提示された条件でした。
ただ料理を作りましたという内容であれば、さっと目を通して、ハンコを押され、返却されるだけだ、ということです。
そんなレポートにはしたくない…
こうして慣れない料理と「おもしろい」という高いハードルに少し戸惑いながらも、試行錯誤の料理研修がスタートしました。
これから料理を始める方や、アサヒ軽金属の調理器具を使ったことがない方の参考になればという思いから、私の料理レポートを皆様にご紹介したいと思います。
それでは早速、私のレポートをご覧いただきましょう。
研修レポート 「白ごはん」 ~入社1日目~

料理研修1回目は、日本人の主食である「白ごはん」を作ろうと思います。
白ごはん。
それはまるで何色にも染まっていない、真っ白な新入社員のようです。
これからの仕事の中では納豆やたくわんを武器にして製品開発に挑んだり、はたまた炒飯のように炒め、混ぜられる慌ただしい日々が訪れるのだと覚悟しています。
さて事前に上司から得た情報によれば、活力なべ(圧力鍋)で炊いた白ごはんは、炊飯器で炊いたものよりモチモチして食感がよいということです。
私の家では炊飯器で炊いた白ごはんを食べていますが、調理の道具が変わるだけで本当に違いが出るのでしょうか。この点に留意して調理を行っていきたいと思います。
私は料理の経験がない素人です。
調理できるものといえば、カップラーメン程度です。
全くの素人に高性能な活力なべを使いこなせるのか多少の不安がありますが、5重の安全システムが搭載されているとわかり、安心して使用できると感じました。
それではレシピ集を見ながら調理を進めます。手順は以下の3つだけです。
- 活力なべに水につけておいた白米と水を入れる
- 加熱する
- 蒸らす
火にかけてしばらくすると蓋についているオモリが振れて、なべの内部にしっかり圧力が掛かったことを知らせてくれます。
その後火を止めたら、なべの中の圧が抜けるのをしばし待てば完成です。
想像していたよりも早く、簡単に炊き上がったので驚きました。
↓炊く前

↓炊いた後

炊飯は成功した様子です。素人メシ(シロメシ)が炊き上がりました。
いつもの白ごはんと比べて、艶と透明感があるように感じます。
全体をかき混ぜた後、早速、できたてを試食してみます。
「モチッ」
とした食感で、もち米のような食感と甘さがあります。
いつも食べているお米と同じなのに、まるで別のお米のようです。
気付けばおかずなしで一膳平らげていました。これが高圧力調理の成せる技なのでしょうか。
調理器具が変わっただけで、これほど食感や味に違いが出るものだということを身をもって体験し、料理の奥深さを垣間見ました。
同居している両親にも好評で「いつものごはんよりおいしいし、省エネだし、時間もかからないね。
これからは炊飯器でお米を炊くことがなくなりそう」と話していました。
この日を境に活力なべでお米を炊くようになり、これまで長らく我が家の食卓を支え続けてくれた電気式炊飯ジャーはもはや「ごはん保温専用機」と化しました。
↓わが家の優秀なごはん保温専用器

今回のレポートは以上です。
初めて活力なべを使ってみて、素人でもモチモチしたおいしい白ごはんが手早く作れてしまうところが、活力なべの実力なのだと感じました。
これまで一番おいしいと思っていた行きつけの定食屋の白ごはんより好みの味です。
まだまだ新人の私ですが、将来はそんな活力なべのように立派な仕事ができる人間になるよう努力していきたいと思います。
※圧力鍋のメーカー・機種によって仕様が異なるため、使い方および注意事項にも違いがあります。
必ず購入した圧力鍋の取扱説明書をよく読み、ご使用ください。
※コラム掲載にあたり、レポートは多少加筆しています。